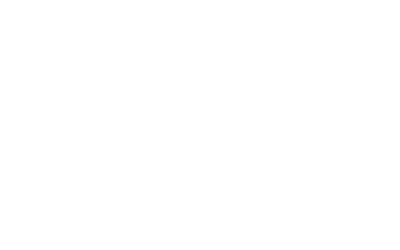2024年6月現在、「AI なくなる仕事」というワードは、ひと月に数千回ほど検索されています(*1)。それに呼応するかのように、さまざまなWebサイトでは「AIによってなくなる仕事10選」「なくなる仕事ランキング」「消えない仕事」などの言葉が踊っています。
人にとって仕事とは、自己安全や自己実現に関わるもの。「AIに自分の仕事を奪われるのでは」と不安になるのも無理もないのかもしれません。そんな不安をぼんやりとでも感じている人にお勧めしたいのが、2024年3月発行の書籍『AI・機械翻訳と英語学習 教育実践から見えてきた未来』です。
・・・・・・・
英語学習?何の関係があるの?と思うかもしれません。この書籍の編者である山中司教授は、立命館大学で展開されている「プロジェクト発信型英語プログラム(PEP)」の推進者の1人であり、「AIや機械翻訳の飛躍的進化により、大学や大学院における英語教育がどうなるのか」が、この書籍の主題となっています。本来想定されている読者は、教育関係者や大学生・大学院生などでしょう。
しかしながら、この書籍には「教員として生き残るためのレゾンデートル(存在意義)」(p.78)を問われている教員たちが、「AIテクノロジーがもたらす激震」(p.266)に真正面から向き合い、それぞれの問いや想いを起点に、挑戦し学び続ける様子が記録されています。
示唆に富む学術書でありながら、アカデミアの住人ではない我々までもがこの書籍から熱量を感じるのは、山中教授をはじめ、このプロジェクトに係わる先生たちが、前例のない事象に対して「自分たちが率先してたたき台となることを覚悟」(p.129)しているからかもしれません。そのような書籍である故、この書籍は教育業界にとどまらず、より広い読者にとって価値があるものと考えます。
・・・・・・・
もう少し具体的に内容に踏み込んでみましょう。この書籍では9人の先生方が、それぞれの専門領域におけるこれまでの研究をもとに、以下のような問いと仮説を立て、実践し評価をしています。
いくつかの企業においてはAIの導入をすすめ、その効果を測っているところもあるかと思います。また、そのような取り組みがメディアで紹介されていたりもします。しかし、そういったメディアの報道でも、この書籍ほど詳しく且つ赤裸々に、AI翻訳 や生成AIの導入について、具体的な活用法と実験的試み、およびその結果について紹介しているものは無いでしょう。
AIの社会実装により、自身の仕事が奪われてしまわないかと不安な人には、本書籍の執筆者のひとりである、立命館大学 近藤雪絵准教授の言葉を贈りたいと思います。
“少なくとも大学において、言語に特化した学部以外で教鞭をとる英語教員の役割は、根本的な変化を迫られている。(中略)問いを立て、調査を行い、批判的に分析し、コミュニケーションを取りながら協同し、知見を発信する、これら知的探究活動を英語で行う広義の科学者としてのいわば「背中を見せる」ことにあるのではないか。”(p.79)
みらい翻訳は、立命館大学「プロジェクト発信型英語プログラム(PEP)」チームと、共同研究を行っており(*2)、その縁で、9人の先生方に並び、この書籍の1つの章の執筆機会をいただきました。実は執筆中は他の先生方が何を書かれるか知らず、書籍が出来上がってから初めて全体に目を通しました。フラットな立場で、本記事を書いていること、お伝えしておきます。
(*1)複数のキーワード検索数算出ツールを使って出した数字です。(*2)立命館大学 2022年10月3日プレスリリース
「大学の英語授業にAI自動翻訳サービスを試験導入 学生・院生約5,000人を対象に、翻訳ツールを用いて新しい英語教育の可能性を検証」
みらい翻訳 2023年7月13日プレスリリース
「AI 自動翻訳「Mirai Translator®」の利用により学生の自作英文への評価と、英語での情報発信に対する自信が向上 -立命館大学「プロジェクト発信型英語プログラム(PEP)」との共同研究成果 第 1 弾-」
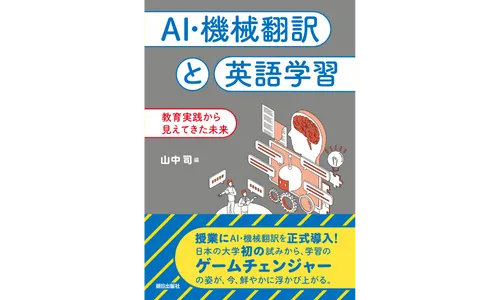
『AI・機械翻訳と英語学習 教育実践から見えてきた未来』
山中 司 編(朝日出版社、2024年)
必修の英語授業にAI・機械翻訳を正式導入した立命館大学。日本の大学初のその試みから見えてきたものは何か。…