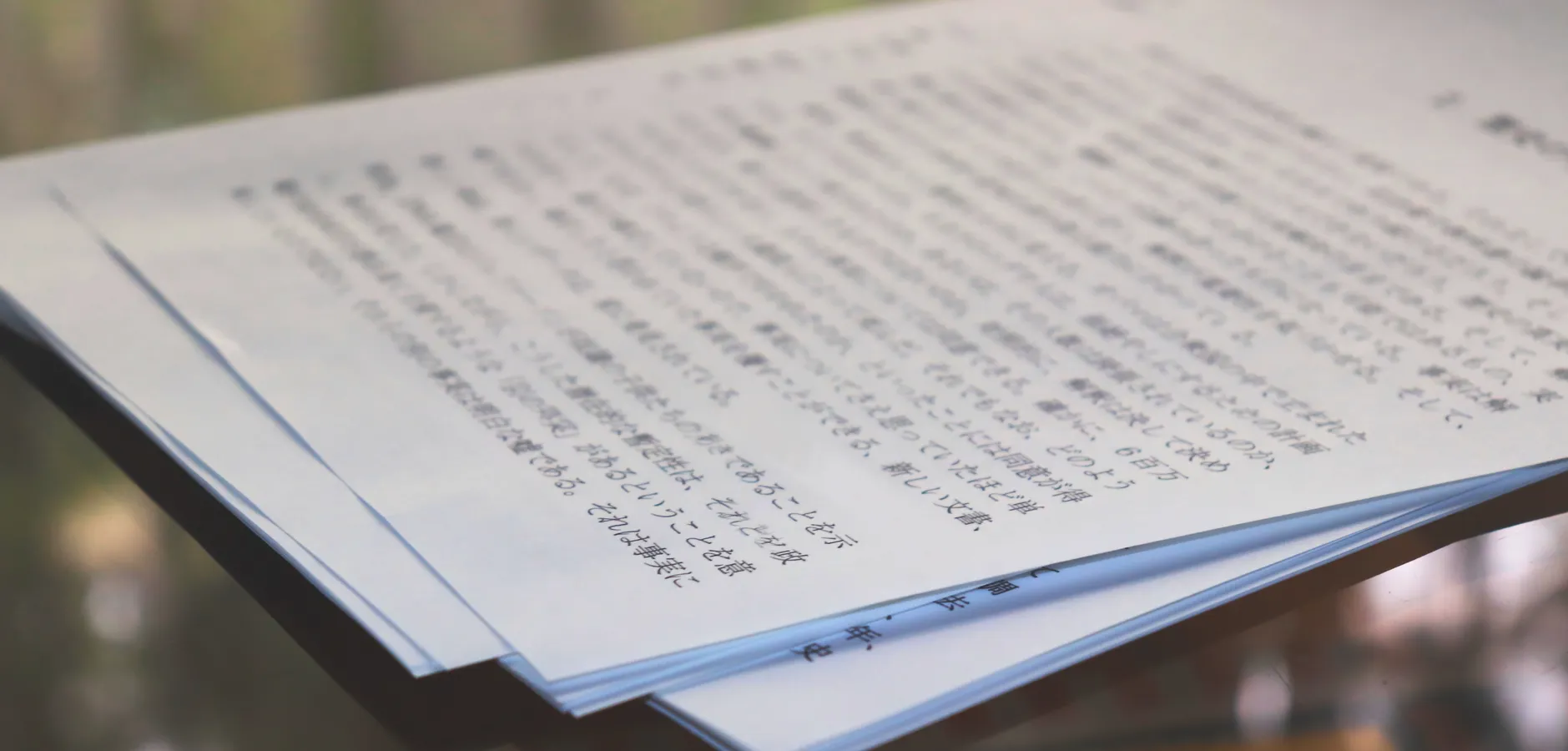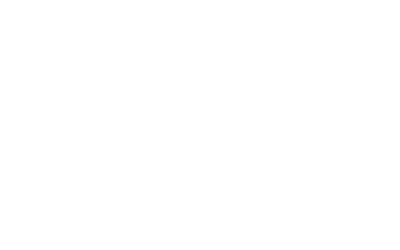情報があふれる現代のビジネス環境下で、企業や行政、団体がステークホルダーにどのように情報を伝えるか。それは、ビジネスの成功を左右する重要な要因です。しかしながら、専門用語が多く複雑な文章や、具体性のない抽象的な文章で受け手に誤解を招いたり、理解しづらいまま発信されたりしているケースが少なくありません。プレインランゲージは、読者をイメージし、誤解なくわかりやすい表現で意思疎通を図ることで、情報を発信する側と受け手、双方の生産性を向上させる手法として注目されています。
今回は、英文IRを強みとする翻訳・通訳会社エイアンドピープルの代表取締役で、一般社団法人日本プレインランゲージ協会代表理事を務める浅井満知子さんにお話を伺いました。浅井さんが考える「プレインランゲージ」とは、単に誤解なく、わかりやすいというだけでなく、IR情報であれば、最終的には資本コストの削減にもつながるとのことです。情報発信において「円滑な意思疎通」を実現するために必要なポイントについて考えます。
目次
プレインランゲージとは何か
――「相手に理解を促すだけでなく、発信する情報の目的、論点、論拠、己を鑑みるツール」
みらい翻訳(以下、M) まず「プレインランゲージ」とはどのようなものか、簡単に教えていただけますか?
浅井さん プレインランゲージは、実務的な情報発信のための「コミュニケーションツール」です。発信には必ず相手がいて、目的があります。発信する側は情報をただ流すだけでなく、「相手に情報を伝え、適切に判断してもらい、目的に沿って行動につなげてもらう」もしくは、「注意喚起してもらう」といった意図があります。しかし、受け手にその情報の意図が伝わらなければ、発信する側も、また受け手もその情報を活用できず、情報発信の目的が果たせません。
現在、日本では「説明責任(アカウンタビリティー)」という言葉が広く根付き、政府、企業、団体などにおいては、明瞭で誤解のない情報発信が奨励されています。それはただ情報を発信するだけではありません。情報の受け手に正確に理解され、的確な判断を下してもらうことで、その説明の義務を果たしたことを意味します。さらにアメリカでは、公的文書はプレインランゲージで記述することが法律で定められており、ISOも2023年にはプレインランゲージを国際標準規格(ISO24495)として正式発行しました。
円滑な意思疎通は、関係者からの問い合わせとその対応の手間暇の削減につながり、双方の生産性を高められます。何より、明瞭で具体性があり、ロジカルな発信は、誠実さと相手を重んじる印象を与え、相互の信頼構築にもつながります。さらには明瞭な文章を書くために、受け手をイメージし、相手に何を訴え理解してほしいのか、そのために自分が情報整理をし、相手にどんなアクションを期待しているのかの自問自答が、最終的には自らを鑑みることにつながります。
M プレインランゲージを取り入れることで企業はどのような成果を得られるのでしょうか?
浅井さん ISOプレインランゲージ規格の「主導原則」には、「①必要な情報が簡単に見つけられる工夫、②スピーディーに要点が理解できる工夫、③簡潔で明瞭な表現を使い、誤解をまねかない工夫、④読みやすさと読み疲れさせないための配慮をすること」が記されています。それは「情報を発信する側と受け手側の双方にとって、お金と時間の節約ができ、信頼構築につながる」とされています。ISO加盟国(日本語を含む27言語)が同じ理念の下、同じガイドラインに準拠して情報配信することで、円滑な意思疎通を図ろうというものです。
たとえば、株主向け報告書では、複雑な用語ばかりだと投資家が内容を理解するのに苦労し、最悪の場合、ゴミ箱に捨てられてしまうかもしれません。もしくは「わざとわかりにくい表現を使い、何か隠し立てしているのではないか?」と、発信者が悪意を持っていると勘ぐられてしまう可能性もあります。さらに利害関係者であれば、訴訟リスクが生じる恐れもあります。プレインランゲージでシンプルに整理された報告書であれば、一読して理解でき、誤解なく伝わり、関係者の有限の時間を有益に使う手だてとなります。
M 投資家が情報をより理解しやすくなることで、どのような効果が期待できますか?
浅井さん 私はよくセミナーなどでお話をする際に、参加者に読者をイメージすることをその場で実践してもらいます。例えば、相手が世界三大投資家だったとします。彼らにとって一番重要なものは何でしょうか?情報もしかりですが、「時間」ではないでしょうか?
忙しい彼らが求める情報は結論、ポイント、要旨です。よって、それらをなるべく文頭に書き、次いで具体的な計画と施策。そしてリーダーとしての経営陣の専門性や経験に基づく自信、そして財源の根拠と人的資源の配分を順に並べると、より理解も促進されます。長期的に投資を続けるか、さらなる投資を検討するかといった判断がしやすくなります。
また、企業側にとっても、明瞭な情報開示を行うことで、好感を得て信頼性を高めることができます。結果的に資本コストの削減につながるという大きなメリットもあります。そうした姿勢やコミュニケーションポリシーは投資家に向けてだけでなく顧客とのコミュニケーションにも役立つでしょう。企業が、顧客、従業員、取引先との「対話」において、親しみやすさ、誠実さ、公正な姿勢を示すことは、共感を生み出し、信頼の構築へとつながります。そうしたコミュニケーションポリシーは、ブランドイメージを高め、顧客満足へとつながり、企業価値の向上に寄与します。
情報過多の時代――受け手に選ばれる情報とは?
M 多くの情報があふれている今、特に企業にとってプレインランゲージが必要な理由は何でしょうか?
浅井さん 今は情報過多の時代で、すべての情報を読み込むのは不可能ですよね。複雑な文やわかりにくい情報は後回しにされ、結局読まれないことも多いです。IR報告書などの企業情報も、何度読んでも理解しにくいと「あとで読もう」とされてしまい、そのまま廃棄されることも。プレインランゲージは、情報を一読で理解できるように整理する手法ですから、受け手が情報を迅速に理解できるようになり、重要な内容が相手に届きやすくなります。
M つまり、読者の「読まない選択」を防ぐためにもプレインランゲージが有効ということですね。
浅井さん その通りです。情報の受け手が、興味を持つ前に読まれないのは大きな機会損失です。特に時間が限られているビジネス層に対しては、短時間で理解できる情報が喜ばれます。ですから、プレインランゲージで「一読で理解できる」状態にすることが、企業メッセージの価値を引き出すためのポイントです。
二つの誤解――プレインランゲージは単なる技法ではない
M わかりやすくするための表現技法と思われがちですが、それだけではないのでしょうか?
浅井さん そうですね、プレインランゲージに関して二つの誤解があります。まず、単なる「やさしい日本語」だと思われること。そして、「一文を短くする」「能動態を使う」などのテクニックだけで、意思疎通が図れると思われがちなことです。しかし本質は「何を伝えたいのか」「目的をどう理解してもらうか」にあります。コンテンツや具体策がしっかりしていなければ、どんなに表現を工夫しても効果は薄いのです。
M テクニックに頼るだけでなく、企業の伝えたい「本質」を明確にする必要があるのですね。
浅井さん その通りです。また、日本語の文書を英語に翻訳して海外へ発信する場合でも、元の日本語の文書がプレインジャパニーズでなければ、プレインイングリッシュとして仕上げるのは非常に難しいです。原文の段階で、内容が明確でわかりやすく整理されていることが前提となります。翻訳時に文意を補ったり再整理したりすると、誤解やニュアンスのずれが生じるリスクが高まります。まずは日本語の段階でプレインジャパニーズを意識し、受け手の立場から情報を整理することが、企業のグローバル情報発信を成功させる第一歩です。
M 日本語での発信内容の質が、そのままグローバル展開における成果につながるのですね。
浅井さん そうです。日本語文書をプレインジャパニーズとして整理することで、翻訳工程がスムーズになり、結果として誤解なく正確に伝わるプレインイングリッシュの文書が生まれます。これは単なる技法ではなく、発信の基盤を整えるための戦略的なアプローチといえます。
日本語の持つ「ハイコンテクスト性」とグローバルなコミュニケーション
M プレインランゲージを導入する際には、日本語固有の課題もありそうですね。
浅井さん 日本語は「ハイコンテクスト」な言語で、言葉の中に多くの意味が含まれています。それが日本語ならではの美しさでもあると思います。しかし、実務情報やグローバルな情報発信においては、こうした複雑なニュアンスが逆に伝わりにくく、障壁になることもあります。いわば「ローコンテクストな表現」を標準とする場面が増えています。企業のメッセージを、多様な文化の違いを理解しつつ整理して届けることが、今の時代に求められています。
M グローバルコミュニケーションにおいては、時代や目的に応じた表現が求められるということですね。
浅井さん そうです。優れたハイコンテクストな日本語を文芸的に尊重しつつ、実務面においてはわかりやすさが求められています。EUを例にとると、24の多言語、多文化の共同体であるEUは誤解を招かず効率的な意思疎通が極めて重要であるため、プレインランゲージで公的文書を24言語で訳しています。グローバル化とデジタル化が進んだ現代社会では、多様な不特定多数の相手に配慮した表現が求められています。
スピーディーな情報発信――AI翻訳の速さと人間翻訳の使い分け
M 情報をどう伝えるかは、タイミングも重要だと思いますが、AI翻訳の活用についてはいかがでしょうか?
浅井さん AI翻訳の進化はめざましく、特に「速さ」においては圧倒的な価値があります。情報は新しいほど価値が高く、発信が後ろ倒しになればなるほど陳腐化する可能性が高まります。即時性を重視する情報にはAI翻訳が非常に有効です。正確性が求められる、例えば相手に承認、共感を得る文章にはAI翻訳の訳文の採用には慎重になる必要があります。(現段階では)
日々進化するAI翻訳は、スピーディーな情報発信が求められる現代のビジネスシーンにおいて利用価値が高いと思いますので、私個人としては肯定的にとらえています。
M なるほど。では、AIと人間の使い分けはどのように考えれば良いのでしょうか?
浅井さん 翻訳に限定せずにお話しすると、膨大な情報から最適と思われる情報を短時間に文章にしてくれるAIはあながち否定はできません。しかし、自社の具体的な経営戦略・戦術、施策をAIが考えてはくれません。人間の役割はそこにあると思っています。
浅井さん 「自分の意見を持ち、議論の中でそれを主張できる力」、「考えの違う人を排除するのではなく、異なる点を理解し、自分の考えと融合して新たな付加価値を模索、創造する力」、「それを異なる意見の相手も巻き込んで現実に実行する力」、それが人間の役割だと思っています。
M そうした使い分けが、情報発信全体の戦略を高めることにつながるのですね。
浅井さん その通りです。AI翻訳の速さを最大限に活かしつつ、内容によって人間の翻訳を取り入れることで、企業メッセージをより正確に、タイムリーに届けられるようになります。情報があふれる現代では、ただ発信するだけでなく、誰もが戦略を持ってコミュニケーションに取り組むことが求められていると思います。
経営陣の意識が変革のカギ――トップダウンでの導入が成功のポイント
M 企業がプレインランゲージを導入する際、経営陣の理解や協力が必要だと思いますが、どのようなポイントがあるでしょうか?
浅井さん プレインランゲージの導入には、経営陣がトップダウンで方針を示すことが欠かせません。現場でいくら努力しても、組織全体での合意がなければ意思疎通は難しいです。また、単に規制に従って形式を整えるだけではなく、投資家に「この会社は価値がある」と感じてもらえるように内容を明確にすることが必要です。欧米ではこの点が非常に重視されていますが、日本企業も見習うべきだと感じます。
M 経営陣のリーダーシップが、情報発信の品質にも影響するということですね。
浅井さん そうです。経営トップが明確な方針を持ち、その意図が社内で共有されてこそ、発信内容もブレなくなります。組織全体での意識改革が、企業全体の価値を上げるための第一歩だと思います。
まとめ
プレインランゲージは、企業の「伝えたい内容の本質」を効果的に届けるための重要なツールです。単に言葉をシンプルにするだけでなく、企業が持つ独自のメッセージを丁寧に整理し、受け手に確実に届けることが今の時代に求められています。浅井さんが強調されている「コンテンツありき」の視点は、情報過多の現代において、企業が他と差別化し、信頼と価値を確実に伝えるための大きなヒントとなるでしょう。
プレインランゲージについてさらに詳しく知りたい方は、浅井さんの著書『伝わる短い英語―アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア 政府公認 新しい世界基準Plain English』や『プレインジャパニーズの教科書』をご覧ください。
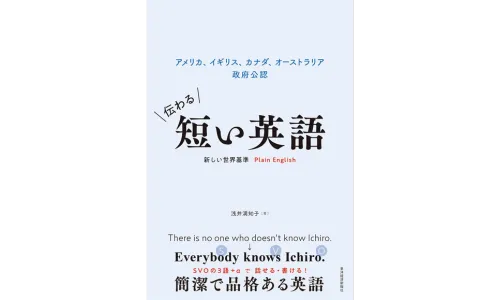
『伝わる短い英語―アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア 政府公認 新しい世界基準Plain English』
浅井 満知子 著(東洋経済新報社、2020年)
書ける!話せる!伝わる!プレインイングリッシュをていねいに解説
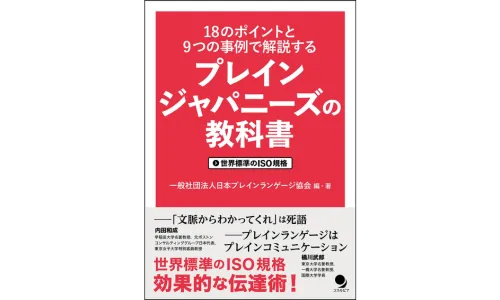
『プレインジャパニーズの教科書』
一般社団法人 日本プレインランゲージ協会 著(コスモピア、2024年)
「文脈からわかってくれ」は死語—内田和成(早稲田大学名誉教授、元ボストンコンサルティンググループ日本代表