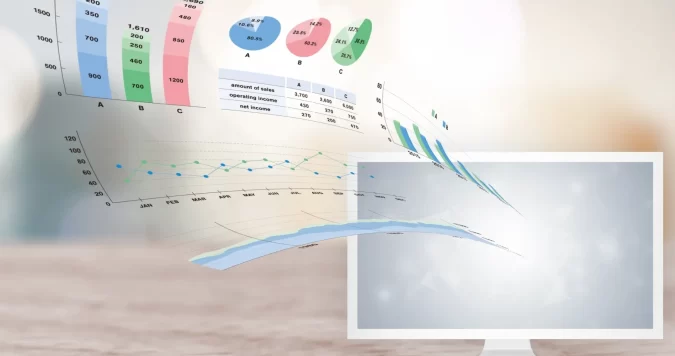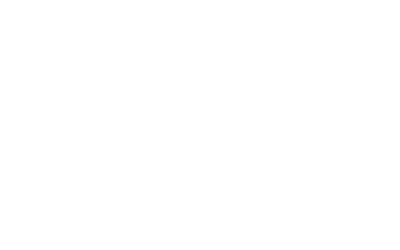2023年初頭、生成AIの隆盛を受けて、みらい翻訳では「Code Red(緊急事態)」が発令されました。2010年代からこれまで、機械翻訳の分野ではニューラル機械翻訳(Neural Machine Translation:NMT、いわゆる「AI翻訳」)が、その精度の高さによって支持を集めてきましたが、生成AIがそれに匹敵する精度を実現し始めたことで、NMTの競争優位が脅かされる可能性が出てきたのです。
「Code Red」発令から2年が経過した2025年現在、その懸念はどうなったのか、現在の生成AIとAI翻訳をどのように捉えているか、AI技術によるビジネス変革はどのように進むのかなど、AI開発の専門家である、みらい翻訳CEO兼CTOの鳥居 大祐氏に話を聞きました。
(※このインタビューは2025年1月末に実施されました。)
目次
「Code Red」発令の背景:生成AIは脅威か!?
みらい翻訳ブログ編集部(以下、M):2023年の社内キックオフで「Code Red」が発令されました。当時、どのようなことが危機的であると感じられたのでしょうか?
鳥居:主な懸念点は2つありました。1つは、翻訳が生成AIの機能の一部として包含され、AI翻訳だけのツールが不要になってしまうこと。そして、もう1つは、企業に対してさまざまなサービスやソフトウェアを提供しているマイクロソフトが、ChatGPTの開発元であるOpenAIと提携しているということでした。生成AIによる翻訳機能が高度化し、マイクロソフトのソフトウェアに組み込まれてしまったら、そこにみらい翻訳が入り込むのは不可能ではないですが相当難しくなるでしょう。
鳥居:ただ、みらい翻訳のソリューションに対抗しうる翻訳サービスが出たというわけではありません。事象として起きていたのは、AIが一段階進化を遂げたということですから、会社のメンバーには危機感を共有しつつも、このAIの進化を取り込んで、私たち自身も新しい状況を創り出せるよう、みんなで考え議論していこうと伝えました。
M:社内で具体的に取り組んだことはありますか?
鳥居:たとえば、エンジニアリング部門では生成AIの性能や特性を徹底調査し、NMTと生成AIそれぞれの特性や強みを明らかにしていきました。それぞれの社員がAIに触れたり技術論文を読んだりということを日常的にやっていました。得られた情報はチーム内で常時共有され、これを取りまとめたトレンド情報を、四半期ごとの全社会議などのタイミングで会社全体にも発信しています。また、当時は「みらい翻訳Plus」の開発中でもあったので、生成AIを取り込んだサービスを目指しました。その後「みらい翻訳Plus」は、作成した英文の文法チェックや丁寧な表現への書き換えなど、生成AIが得意とする機能を盛り込んだ「ハイブリッドAI翻訳サービス」として、2024年1月末にリリースされています。
AI翻訳と生成AIの現在地
M:「Code Red」発令から2年が経過した現在の状況をどう見ていますか?
鳥居:企業の中で生成AIの導入が進んでいったとは思いますが、多くの企業では「生成AIだけあればいい」という状況にはなっていません。生成AIは導入しなければならないという思いが先行し何に使っていくか手探りなのに対し、言語の壁を越える翻訳に対するペインは根本的に強く、それに対処することは企業の生産を上げる明瞭な手段として大きな関心事である状況は変わりません。生成AIによる翻訳は、処理に時間がかかるほか、表現は流暢であるものの訳出されない要素があるなど、対訳として正確かという観点では課題もありますし、翻訳に特化されたインタフェースになっていません。例えば、訳文に対し別候補を提示したり、辞書を参照したり、逆翻訳で訳文の正しさを確認したり、といった機能です。また、Office文書やPDFなどレイアウトを保持したまま翻訳する機能も根強いニーズです。こういう状況を鑑みると、NMTか異なる技術であるかはさておき、翻訳に特化されたサービスの必要性自体が急激にしぼむということは、今すぐには無いだろうと捉えています。
M:では、「Code Red」の状態からは抜け出たという認識でしょうか?
鳥居:生成AIも日々進化しているので、「Code Red」を完全に抜けたとはまだ言えないでしょう。みらい翻訳が完全にユニークなポジションに立てている訳ではないことを意識しながら、翻訳とAIの専門集団として、企業の生産性向上に寄与するベストなソリューションを提供し続けることが重要だと考えています。
生成AIがもたらした市場の変化
M:その他に、ここ2年の市場の変化として何か感じていることはありますか?
鳥居:生成AIの登場により、企業のセキュリティ意識が高まったということはありました。生成AIの中でも、無料で使用できるものは特に、情報漏洩のリスクや法的リスクと背中合わせです。そういったことを知らないまま、社員がむやみに使ってしまうのを防ぐ必要があるということで、自社のセキュリティ要件の再確認や社内の状況把握を行った企業のお話をよく聞きます。この、セキュリティ意識の高まりは、自社開発・国内サーバ完結で高いセキュリティを誇る、みらい翻訳のサービスにとって追い風となりました。実際に、生成AIをきっかけに無料ツールの利用によるセキュリティリスクへの認識が高まり、無料の翻訳ツールに代わるものとして、弊社の「FLaT」を導入いただいた企業もあります。
鳥居:それからもう1つ、生成AIの登場よって、翻訳に対する見方やニーズが変化してきていると感じています。機械翻訳はNMTの時代になって飛躍的に精度が向上しました。それでも100%の正解は無いので、あくまでも補助的なツールという位置づけで使われてきました。しかし、生成AIの出現により、より踏み込んだ、完成度の高い翻訳やカスタマイズ可能な翻訳サービスへのニーズが出てきています。たとえば、生成AIのようにチャット形式で相談しながら翻訳文を編集したり、チェックして提示したりといった機能を付加して、翻訳文の最終化までできないか、というような期待が高まっています。
M:そのような期待に応えていこうという予定はあるのでしょうか?
鳥居:翻訳文の最終化支援というのは、実は簡単なことではなく、実現にはかなりのノウハウが必要です。だからこそ、AIや言語処理に関する専門技術や知見を持っているみらい翻訳がチャレンジすべきことだと思っています。NMTと生成AIのベストミックスを目指して、高品質な翻訳やカスタマイズ性の高いサービスを提供していく方針です。
AIのビジネス活用はどう進む?
M:さまざまな企業から、生成AIについての質問や相談を受けることも多いそうですね。日本のグローバル企業における生成AIの活用は、鳥居さんからどのように見えていますか?
鳥居:多くの企業では、とにかく生成AIを入れてみよう、使ってみようというところからスタートしていると思います。汎用的な生成AIを使って、どんな業務でもいいから効率化を図ろうというのが第一段階。それが第二段階になると、より業務特化の方向に進むという印象があります。つまり、それぞれの企業における重要な活動の一部にAIを組み込んで効率化を目指すという方向です。そのために社内勉強会をしたり、アイデアを出し合ったりという会社もあります。それで、思い描いた理想のAI活用に向けていろいろと試してみるけれども、現実はそう簡単ではなくて、よくわからないけれどうまくいかない、というようなところで相談をいただくケースが多いですね。
M:そういった相談にはどのように応えるのでしょうか?
鳥居:お話をうかがってみると、AIをどこに適用させて、どうソリューションさせれば意味のある効果が出せるかということが、明確になっていない気がしています。「意味があるもの」をちゃんと特定して理解する・言語化することが重要で、それができればソリューションできると思います。ですので、まずはその「理解・言語化」のプロセスをご一緒すること。次に、実際にソリューションを開発・適用するステップになっていくわけですが、そこでは、みらい翻訳がやってきたチューニングの知見などが生かせると思います。
M:そうなると、もはや「翻訳」の領域だけでは留まらない気もしますが、みらい翻訳としては、今後どのように舵を切っていこうと考えていますか?
鳥居:先ほどお話した、翻訳に対するニーズの変化を踏まえても、「原文をできるだけ正確に別の言語に変換する」という狭義の「翻訳」をやっていくだけでは、企業の生産性向上を押し上げるには足りません。より広く「言語」にかかわるサービスプラットフォーマーとして、NMTのさらなる高度化はもちろんのこと、生成AI活用や音声対応など、幅広い業務効率化ニーズに応えていきたいと考えています。