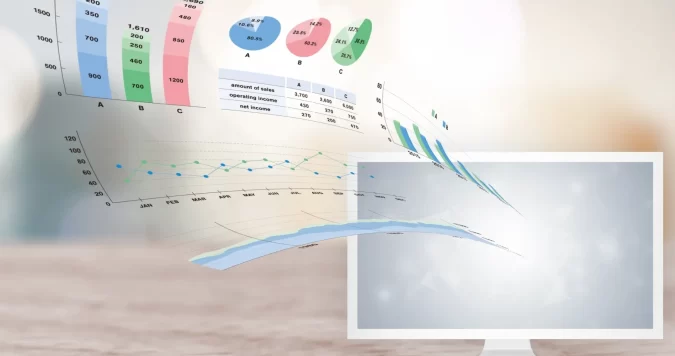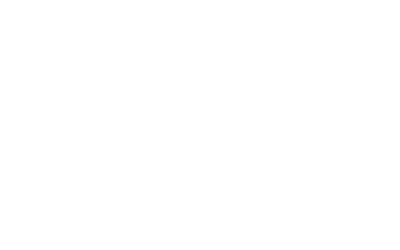※この記事は2025年9月17日に更新しました。
「導入を検討しているAIツールのセキュリティ、本当に信頼できるだろうか?」
このような課題をお持ちのDX・情報システム担当者の方も多いのではないでしょうか。
近年、多くの企業でクラウドサービスやAIツールの導入が進んでいます。業務の効率化に大きく貢献する一方で、私たちが入力する機密情報が漏洩するリスクも高まっています。
そこで重要になるのが、導入を検討しているサービスのセキュリティが信頼できるかどうかを客観的に判断するための「第三者認証」です。
本記事では、特に近年注目を集めている「SOC 2(ソックツー)報告書」について、同じく情報セキュリティ認証として知られるISMS(ISO/IEC 27001)やISO/IEC 27017との違いを交えながら、分かりやすく解説します。
目次
SOC 2とは何か?
SOC 2とは、米国公認会計士協会(AICPA)が定めた「Trust Services Criteria(信頼サービス原則)」に基づき、企業のセキュリティ体制が信頼できるものであることを監査法人などの第三者が検証し、その結果をまとめた報告書のことです。
最大の特徴は、セキュリティに関する規定やルールが単に「設計」されているかだけでなく、そのルールが実際に「運用」され、有効に機能しているかを評価する点にあります。
この「SOC 2報告書」という客観的な証明があることで、サービス利用者は安心して機密情報を預けることができるのです。
重要ポイント:継続的な信頼性を示す「Type 2報告書」
そのSOC 2報告書には、「Type 1」と「Type 2」の2種類があり、どちらの報告書かによって信頼性のレベルが大きく異なります。サービスを選定する上では、この違いを理解しておくことが非常に重要です。
- Type 1報告書:特定の時点において、セキュリティに関するルールが適切に設計されているかを評価します。
- Type 2報告書:一定期間にわたり、そのルールが有効に運用されているかを評価します。
サービスが継続的に安全であることを示す、より信頼性の高い証明となるのがType 2報告書です。サービス選定の際には、「SOC 2 Type 2報告書」を取得しているかどうかを確認することが、信頼できるサービスを見極める鍵となります。
具体的に何をチェックする?SOC 2の評価項目
では、ルールが運用され、有効に機能しているか判断するために、SOC 2では具体的にどのような点をチェックするのでしょうか。SOC 2では「信頼性サービス規準」と呼ばれる、以下の5つの評価項目が定められています。サービス利用者は、提供事業者がどの項目で評価を受けているかを確認することで、自社の要件と合致しているか判断できます。
- セキュリティ:システムが不正なアクセスから保護されているか。(例:アクセス制御、ファイアウォール)
- 可用性:システムが契約通りに利用可能であるか。(例:障害発生時の復旧手順)
- 処理のインテグリティ:データの処理が、承認された通りに実行されているか。(例:データ入力時のエラーチェック)
- 機密保持:機密情報が適切に保護されているか。(例:データの暗号化、アクセス権の管理)
- プライバシー:個人情報が適切に収集、利用、保管、廃棄されているか。
監査人は、これらの項目について、企業の実際の運用状況を一定期間にわたって検証し、「SOC 2 Type 2報告書」としてまとめます。これにより、サービス利用者はそのサービスが継続的に高いセキュリティレベルを維持していることを確認できるのです。(*1)
【例えば、こんな場面で役立ちます】
海外の取引先との機密性の高い契約書の翻訳にAI翻訳サービスを利用したい場合を考えてみましょう。そのサービスが「機密保持」や「プライバシー」の項目を含むSOC 2 Type 2報告書を取得していれば、「預けたデータは長期間にわたり適切に保護・管理されている」という客観的な証明になります。これにより、担当者は安心して業務にツールを活用でき、企業のDX推進とセキュリティ確保を両立できるのです。
SOC 2と他の認証(ISMS/ISO27001, ISO27017)との違い
セキュリティに関する認証として、ISMS(ISO/IEC 27001)やISO/IEC 27017もよく知られています。これらとSOC 2との違いは何でしょうか。
| 認証 | 主な評価ポイント | 特徴 |
|---|---|---|
| SOC 2 Type 2 | 運用状況の有効性 | 継続的な運用実績が証明されるため、特に重要な情報を扱うサービスで有効。 |
| ISO/IEC 27001(ISMS) | 体制の構築 | 情報セキュリティマネジメントシステムの構築・維持・継続的改善を求める国際規格。認証機関により審査・認証される。 組織全体の情報セキュリティ体制の基礎を示すため、企業の信頼性の証明に有効。 |
| ISO/IEC 27017 | クラウドに特化した設計 | ISO/IEC 27002を補完する形で策定されたクラウドサービスに特化した情報セキュリティ管理ガイドライン。 クラウド利用が前提のサービスにおいて、基本的なセキュリティ要件を満たしている証明に有効。 |
簡単に言えば、ISO認証は設計フェーズを重視し、全体のフレームワーク構築に重点を置く。一方、SOC 2はその設計が現実に運用されているかを、証拠に基づき長期間検証する、という違いがあります(*2)
(*2) ISO/IEC 27001も「PDCAサイクル」に基づく継続的な運用管理を求めており、「設計だけ」を評価するわけではありません。まとめ
クラウドサービスやAIツールを安心して利用するためには、そのサービスが信頼できるセキュリティ体制を整えているかを見極めることが不可欠です。
特に「SOC 2 Type 2報告書」は、サービスのセキュリティ体制が継続的に有効であることを示す客観的な証拠となります。「設計」面の認証であるISO認証などと併せて、この「運用」面を評価するSOC 2報告書の有無も、これからのクラウドサービス選定において、不可欠な視点となるでしょう。