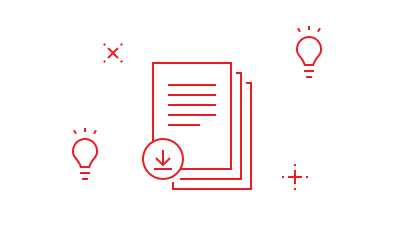株式会社INPEX AI自動翻訳の導入 「翻訳を業務にしている社員はいない」 外国語業務を日常とするエネルギー企業が実現する、自動翻訳と生成AIの共存
株式会社INPEXは、Energy Transformation (EX)のパイオニアとして、石油・天然ガスから水素、再生可能エネルギーまで多様でクリーンなエネルギーの安定供給を目指すことで、ネットゼロカーボン社会の実現に向けた取組みを推進しています。国内外でのエネルギー資源の確保と供給に努め、特にオーストラリアの「イクシスLNGプロジェクト」や「アブダビ油田プロジェクト」など、大規模なプロジェクトを推進しています。また、クリーンエネルギーの分野にも積極的に取り組んでおり、水素や再生可能エネルギーの事業開発を通じて、持続可能な社会の実現を目指しています。
同社では、2023年11月より『FLaT』の正式利用を開始。本記事では、INPEX資材・情報システム本部のITサービスグループ Manager 森 真之助様、ビジネスソリューショングループ Business Analyst 中島 暁平様、保険グループ/プロジェクト調達グループ Risk and Insurance Analyst 石井 千尋様に『FLaT』の採用の理由や活用状況を伺いました。
株式会社INPEX
株式会社INPEXは、エネルギーの開発・生産・供給を担うリーディングカンパニーとして、日本企業初の大型LNGプロジェクトの操業主体(オペレーター)である「オーストラリア イクシスLNGプロジェクト」など、国内外で事業を展開し、長期的な視点でエネルギー供給を支え、持続可能な未来の実現を目指しています。また、日本と世界へのエネルギー安定供給の責任を果たしつつ、Energy Transformation (EX)のパイオニアとして、石油・天然ガスから水素、再生可能エネルギーまで多様でクリーンなエネルギーを安定供給し、2050年ネットゼロカーボン社会の実現に向けたエネルギー構造の変革に積極的に取り組んでいます。
ご担当者様
資材・情報システム本部 情報システムユニット ITサービスグループ Manager 森 真之助(もり・しんのすけ)様
資材・情報システム本部 情報システムユニット ビジネスソリューショングループ Business Analyst 中島 暁平(なかじま・ぎょうへい)様
資材・情報システム本部 資材・保険ユニット 保険グループ/プロジェクト調達グループ Risk and Insurance Analyst 石井 千尋(いしい・ちひろ)様

同社が日本企業初の大型LNG(液化天然ガス)プロジェクトの操業主体(オペレーター)として、ガス・コンデンセート田を開発・生産し、事業を推進する「イクシスLNGプロジェクト」のCPF(沖合生産・処理施設)(引用元:INPEX企業サイト)
目次
出発点と選択の理由:きっかけはヒューストン駐在員からの進言。コストとセキュリティが決め手で全社導入

森氏
ー 皆さまの業務内容をご紹介ください。
森:私と中島は、去年まで同じチームにいました。情報システム部門の中でも特にAIを活用したサービスを追求するタスクフォースで、SaaSや翻訳なども含めて幅広くサービスの検討や導入を推進していました。
石井:私は、森、中島と同じ本部ですが、資材・保険ユニットの保険グループに所属しており、保険手配を中心としたリスクマネジメントを行っております。
ー 『FLaT』を選定いただくに至った経緯をお聞かせください。
森:当社は事業の特性上、英語を中心としてグローバルな業務に従事する社員も多く、翻訳のニーズも高い環境です。また、ときには産油国や産ガス国の母国語のニュースやドキュメントを参照する必要もあり、例えば、インドネシアで推進している「アバディLNGプロジェクト」などではインドネシア語のニーズもあります。これまでは個々人が無料の翻訳ツールを使用したり、一部の部署で翻訳サービスを導入して使ったりしている状態でした。個々人がセキュリティ意識をもってルールを守りながら利用していれば問題ないのですが、やはりシャドーITなどのリスクもあり、会社としてセキュリティ面で安全な翻訳環境を提供すべきという議論が進んでいました。

世界約20カ国で探鉱・開発・生産プロジェクトを展開するINPEX(引用元:INPEX企業サイト)
最初は、ヒューストンIT担当の駐在員から相談がきたんですよ。「翻訳ツールを使っている社員もいるが、会社統一で安全性の高いものを利用できる環境を作った方がいいんじゃないか」と。みらい翻訳の名前も、最初に出てきたのはこの社員からでした。
こういうツールがあるから当たってみてくれないかと。情報システム部門でもリスクは感じていたので、2023年4月にチームで検討を開始しました。セキュリティの高い翻訳サービス、それも特定の社員だけではなく、できるかぎり全社員が使えるサービス、ということで探し始めました。
ー なぜ全社員で翻訳業務を行うことが重要だったのでしょうか。
森:今、翻訳業務と言われましたが、当社に翻訳を業務としている人はいないんですね。海外プロジェクトを担当する社員は、英語で仕事をするのが当たり前で、誰かに「これを英語に翻訳して」とお願いすることはありません。基本的に英語で業務を行うのですが、文量が多いときなどは一度日本語に変えた方が楽だなといったときに使ったり、社内資料として日英で変換するような時に使ったりします。

中島氏
中島:管理面でも、全社展開した方が圧倒的に管理・運用コストが小さいです。もし仮に翻訳サービスを1,000ライセンス調達して使う人にのみ振り分けるとなったら、誰が使う人なのか、その人が部署を異動したら外すのか、新しく入社した人はどうなのか、と人事異動のたびに作業が発生してしまい、運用がかなり大変です。しかし、全社展開の場合は、全員にライセンスを適用すればよく、異動の度に割り当て状況を管理する必要がなくなるため、一部の社員に展開するより断然楽だと思います。
ー 『FLaT』を採用していただいた決め手は何でしたか。
中島:主に行ったのは無料の翻訳ツールの有料版と『FLaT』の比較検討でしたが、決め手はコストとセキュリティでした。前者は料金形態がユーザーあたりの単価型のライセンス体系で、弊社で全社展開するとなると、コストが非常に高くなってしまいます。一方、『FLaT』は1つのプラットフォームを提供してくれて、サービス全体での料金設定になっており、利用人数に応じた価格変動がないため、コスト面で非常に優れていました。
もう1つ、セキュリティ面として、『FLaT』は、国内サーバにデータを保管することが担保されている点で安心できました。『FLaT』以外で検討していたサービスは外資系企業だったため、ある程度配慮されてはいるとは思うものの、万が一情報漏洩などのトラブルが発生した場合、国外にデータが出ていた場合、漏洩の状況検証に難しさが残る可能性があると考えました。
森:情報システム部門としては、他のサービスを選定する場合でも、セキュリティは特に強く意識していますね。
中島:機能でいえば、トライアルの際、ファイル翻訳が高い評価を受けていました。ファイル翻訳という機能自体は他の翻訳サービスにも存在しますが、『FLaT』の利用時に初めてその機能に触れた社員もおり、それがセキュアな環境下で使えるということが本サービスに対する高い評価に繋がったのだと考えております。
森:当初は2024年1月から全社展開を開始しようと思っていました。しかしマネジメント層からも「早く使いたい」という声が強かったため、前倒しで2023年11月から使い始めました。

GDPRにも対応。機密情報も翻訳できる堅牢なセキュリティ
自動翻訳サービスは、セキュリティが非常に重要。特に機密性の高い情報を扱うビジネス翻訳では、セキュリティが堅牢でないと情報漏洩につながりかねません。みらい翻訳では情報セキュリティに関する国際規格を取得。この要件に準拠して運用しており、高いセキュリティ水準が求められる大手の金融機関や製薬会社でも多数採用されています。
INPEX流の活用術:世界中のプロジェクトのための保険調達業務で活用。正確に把握したいレポートや英文を『FLaT』で確認。細かいニュアンスは生成AIで編集

石井氏
ー どのようにご活用いただいていますか。
石井:保険業務の中で活用しています。当社はさまざまな国で石油やガスを開発するプロジェクトを展開しており、建設工事保険や操業保険及び賠償責任保険等、プロジェクトのフェーズに応じて適切な保険を手配する必要があります。プロジェクトは投資金額も大きく、たとえばオーストラリアで行っている「イクシスLNGプロジェクト」は、投資規模が数兆円にもなります。

「イクシスLNGプロジェクト」の陸上ガス液化プラントではLNG年間約890万トン、LPG年間約165万トンに加え、コンデンセート日量約1.5万バレル(ピーク時)を生産・出荷。(引用元:INPEX企業サイト)
それに伴い、アセットに付保しなくてはいけない金額規模も大きくなるため、ロンドンを中心とした世界中の保険会社にリスクを引き受けてもらう必要があります。そして保険会社にリスクの引受を行ってもらう際には、リスク分析のレポートをエンジニアと共に英文で発行することになります。
リスク分析レポートはかなりの分量があるのですが、一度これを原文で読んでから重要なポイントは翻訳をかけ、自分の理解と合っているかを確認する意味で『FLaT』を使うことが多いです。
また、一日に送信するメールの大半が英文なので、急ぎの時には、日本語で入力すれば英訳してくれるので助かっています。また、言いたいことが伝わるか確認するために、自分で書いた英語を日本語に戻してみるときもあります。こだわっているのはニュアンスですね。当社ではChatGPTのような生成AIのサービスも導入しているので、『FLaT』で訳出した文章をさらに生成AIにかけて「もう少し感謝の気持ちを強めに」というようにブラッシュアップしてもらうこともあります。

森:『FLaT』と生成AIを二段階で利用する方法はとても効果的で、私も重要な資料を作成する時などは、最初に『FLaT』で訳出してから、もう一度生成AIにかけます。
自分が分かればいいという文章は『FLaT』で十分ですが、生成AIを通すと、翻訳からさらに『ニュアンスを変更』してくれます。例えば、アカデミックにしたいとか、ビジネススタイルにしたいとか、いろいろなニュアンスで書き直させることができるので、より精度の高い利用が可能になります。これは翻訳というより編集ですね。それぞれのツールをどう使うかは、社員にどんどんトライしていってほしいです。
導入効果と今後の展望:海外とのスムーズな意思疎通とシャドーITへの危機意識共有が実現。自動翻訳と生成AIをどう共存させるのか

ー どのような点に『FLaT』を利用する価値を見出していただいていますか。
石井:業務の効率化につながったと思います。私自身、自分でも英文は書けますが、ツールがある方が時間も短縮できるし、「こういう言い回しがあったか」と気づきを得て語彙力も上がり、きれいな英語でスムーズに意思疎通できるようになりました。
森:ファイル翻訳をはじめとして、評判がいいです。KPIを設定して何人使っているかといった管理は行っていませんが、サービスに対する社員からの評判は総じて高いと思います。また、『FLaT』が入ったことで、シャドーITという概念を浸透させるいい機会になりました。
世の中にいろいろオープンなサービスがあるけれど、ものによっては安易に情報を入力してはいけないのだ、という自覚を促せたのは成果の一つかなと私は考えています。

ファイル翻訳はPDFやPowerPoint、Word、Excelなどの装飾やレイアウトも原文通り翻訳可能
ー 今後の展望をお聞かせください。
森:生成AIの登場以降特に顕著ですが、サービスの進化が目覚ましいので、常に新しいものを探していく、考えることを止めないというのが情報システム部門のスタンスです。『FLaT』については非常にいいフィードバックをもらっていて、社内に浸透しつつありますが、一方で、+生成AIという使い方も進んでいます。私たちとしては一番効果的と判断したものを、できるだけ多くの選択肢を用意して社員に提供する。社員ごとに業務が違うため、使い方は社員に選択してもらえるようにしていきたいですね。
中島:翻訳ツールもその一つだと考えています。『FLaT』に要望を出すとしたら、ノルウェー語やアラビア語などにも対応して欲しいというのと、例えば有価証券報告書やIFRS対応でも翻訳ニーズがあるので、これらに特化したエンジンがさらにアップグレードしてくれると嬉しいですね。

中島:また、アプリケーションの管理者という立場としては、アプリケーション側でユーザーマスタの管理が不要になることが望ましいです。『FLaT』は人数を問わない料金形態のサービスですから、撤廃することも可能なのではないでしょうか。そうなればさらに管理が楽になるので非常にありがたいです。
石井:個人的には、たとえば日本語から英語へ訳出したときに、単語ごとに別の候補を出してもらえるとうれしいです。これはちょっとニュアンスが違うんだよな、というときに、そこに似た意味でニュアンスの異なる単語の候補が出てくると、さらに便利になると思います。


組織でAI自動翻訳を無制限利用 FLaT
高精度AI自動翻訳を翻訳量・ID数無制限で提供した上で、アセスメント・活用促進も含め提供するワンストップDXソリューション。グローバル化する組織の生産性とセキュリティレベルを同時に引き上げます。