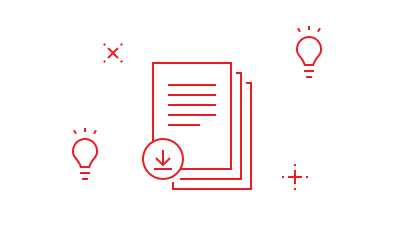ダイキン工業株式会社 AI自動翻訳の導入事例 年間4,000万円相当の業務効率向上効果。グループ展開でグローバル経営の加速を支援
ダイキン工業株式会社は、「空気で答えを出す会社」として空気であらゆる課題を解決し、新しい価値を創造し続けている総合空調専業メーカーです。グローバル経営を推進する同社では、2021年4月より機械翻訳のメジャーツールとして『Mirai Translator®』を国内グループに展開しています。本記事では、導入を統括されたダイキン福祉サービス株式会社 本社統括本部 ビジネスサポート部 担当課長 山田 立人氏、低温事業本部 企画部 村尾 優子氏、サービス本部 グローバルサービス部 ブンジャイ ナワラー氏に採用の理由と活用状況を伺いました。
ダイキン工業株式会社
1924年創業のダイキン工業株式会社は、「空調」「化学」「フィルタ」を柱に事業を展開しています。空調機器と冷媒を両方手がけている総合空調メーカーは、世界を見渡しても他に類を見ません。人と空間を健康で快適にするために、国や地域ごとに異なる文化・価値観から生まれるニーズに応え、多彩な製品とサービスをグローバル市場に提供しています。2025年を目標年度とする戦略経営計画「FUSION25」では、成長戦略3テーマに「カーボンニュートラルへの挑戦」「顧客とつながるソリューション事業の推進」「空気価値の創造」を策定。環境・社会貢献を果たしながら事業も成長・発展させ続けるという強い思いを抱いて日々躍進を続けています。
ご担当者様
ダイキン福祉サービス株式会社 本社統括本部 ビジネスサポート部 担当課長 山田 立人(やまだ・たつひと)様
低温事業本部 企画部 村尾 優子(むらお・ゆうこ)様
サービス本部 グローバルサービス部 ブンジャイ ナワラー様
目次
課題:グローバル経営を加速する中、あらゆる部門で翻訳業務が発生
ー はじめに、皆さまの業務内容を教えてください。
山田:ダイキン福祉サービスは人事本部管轄の子会社で、私はグループのグローバル化を支援する業務を担当しています。この案件では、機械翻訳ツールをグループに普及するための全社コーディネートを行いました。
村尾:冷凍冷蔵機器を扱う低温事業本部の企画部で、海外子会社の管理を担当しています。中・長期の事業計画立案や月次決算管理、コンプライアンス教育などさまざまな業務を担当しています。
ナワラー:グローバルサービス部で、海外販社の営業活動をサポートしています。主な業務は、営業や技術担当者の研修のための資料作成や提供です。

ナワラー氏
御社では、どのような場面で翻訳業務が発生していますか。
山田:現在、当社はグローバル経営を加速させており、すでに77%は海外からの売上高で、事業展開する国は160カ国以上に広がっています。あらゆる部門で、メールのやりとり、資料作成などといった日々の活動に翻訳業務が必要です。それで、2012年からグループに機械翻訳ツールを提供し始めたのですが、AIの登場によって機械翻訳の品質が変わってきたのを実感し、そろそろ入れ替えどきだなと思っていました。
事業の特性上、翻訳業務が必要不可欠なので、各部門で自分たちの業務に合った機械翻訳ツールを導入する動きもありました。村尾の所属する低温事業本部は『Mirai Translator®』を先行導入した部門の一つです。
村尾:私は経理財務部に教えてもらいました。あるとき、私が担当している子会社の決算レポートを翻訳にかけて送ってもらったら、かなりのボリュームだったのに頭の中にすっと大意が入ってきたんですね。今まで使った翻訳ツールでは初めての経験でした。精度が低いものだと、結局ほとんどこちらで手直しすることになり、ツールを使う意味がないと常々思っていたのであれは驚きでした。これは使いたい! と思って、上司に「私たちの部門でも使わせてください」とアピール、導入してもらいました。
山田:こうした動きもあり、入れ替えどきでもありましたから、あらためてダイキングループで利用する機械翻訳のメジャーツールを選定しなおそうということになりました。導入するならグループで契約した方がスケールメリットを出せます。
選択の理由:ファイルごと翻訳できる利便性を高く評価して『Mirai Translator®』を選択

山田氏
ー どのように選定は進められたのでしょうか。
山田:7つの製品・サービスを候補に挙げて、「翻訳品質」「多言語対応の度合い」「セキュリティ対策」「利便性」といった項目で比較検討を行いました。その結果、選んだのは『Mirai Translator®』です。決め手は「利便性」でした。テキスト翻訳という観点では、他にも高い品質を発揮するものもありましたが、ファイル翻訳、文字起こしを含めたOCR機能まで装備したものは他になく、利用者の労務工数削減を考えるとこれが一番だと思いました。
村尾:『Mirai Translator®』のファイル翻訳機能は、ほんとうに優れていると思います。翻訳したい資料はExcelやPowerPoint形式であることも多く、翻訳した文章を元通りレイアウトするためにカット&ペーストを繰り返すとなると、とても時間がかかります。このツールでは、レイアウトだけでなく文字の太さや色などもそのまま維持して翻訳してくれて、とても助かっています。
山田:また、グローバルIPアドレスの登録でアクセスを制限しセキュリティを確保する機能や、ダイキンと同じようなメーカーが他にも何社か利用していたこと、NTTグループやパナソニックがパートナーでありAI学習による品質向上においても製造業向けの進化が期待できるといった点も採用理由です。
2021年1月中旬から1カ月間、公募に応じた全社約200名を対象に大規模トライアルを実施しました。直後にアンケートを行って「週に平均どれくらい翻訳業務が発生しているか」「それがこのツールでどのくらい削減できると思うか」と尋ねて集計したところ、週4.7時間であったものが1.9時間減って2.8時間になるとわかり、また「この先も使い続けたい」という声が8、9割を占めたため、正式に導入を決定。有償トライアル期間を経て、2021年4月、本格展開するに至っています。
グループ子会社まで利用可能な契約を締結するためには、一定規模のユーザ確保が必要であり、当初はそれだけの利用者を確保できるか少し心配でした。150人がその分岐点でしたが、初回の社内PRでその数を超え、その後も口コミで増えていきました。現在は、基本プラン利用者が200名、多言語オプション利用者が50名となり、いまだ増加している状況です。
導入後の感想:翻訳業務工数が1/5~1/10に短縮、4,000万円/年の労務費削減に相当
ー 日々どのようにご利用になっていますか。
ナワラー:冒頭でも触れたとおり、海外の営業や技術担当者のための研修資料を作成しています。当社は海外企業の買収や事業提携でさまざまな製品を取り扱っており、元の資料は日本語、英語さまざまです。私がタイ語で一から資料を作ることもあります。大体はPowerPointベースなんですが、それらを英語、タイ語、ベトナム語に翻訳して現地に展開したり、日本語がない資料に関しては、日本語に翻訳して部内で共有したりしています。

村尾:私は日本語⇔英語、英語⇔日本語で利用しています。海外の子会社というのは具体的にいうとオーストラリアなんですが、現地スタッフとディスカッションして作成した資料を、同時並行で上司や事業部に展開するために日本語に翻訳して提供します。そして日本側で動きが出たら、それを英語にして現地へ。契約案件などはスピード勝負のことも多いため、お互いに「明日までに結論を!」と言い合うような緊迫感のあるやり取りになることもあります。ここで翻訳に時間がかかったりしたら、まとまる話もまとまらなくなるので、精度はもちろんスピードも非常に重要です。
ー 『Mirai Translator®』の利用メリットは、どのような点にあるでしょうか。
村尾:時間短縮ですね。翻訳業務にかかる時間が1/5~1/10になりました。もちろん、チェックや手直しは以前と同様に行うのですが、その労力がまったく違います。作業が減って生まれた時間で、私は考える時間を持てるようになりました。事業の方向性や、課題があるとしたらそれはどのように解決すればいいかなど、より本質的な業務に時間を割けるようになりました。
ナワラー:私もそうです。短時間で3言語の資料が作成できるので、研修の内容についてより深く考えられるようになりました。
山田:業務効率向上効果は高いと思います。これは当社での試算ですが、翻訳業務にかかる工数削減効果は一人当たり年間90時間と見ており、これを労務費に換算すると20万円ぐらいになります。200名ならグループ全体で4,000万円の労務費が削減できることになります。
ー 今後の展望をお聞かせください。
山田:まずは、海外拠点への展開拡大です。利用者が増えることで社内利用料のさらなる低減ができますし、ダイキン福祉サービスにとっては運営収入の増大が図れます。また、長期的には、『Mirai Translator®』が他の自動翻訳サービスに負けない翻訳品質や利便性の向上を実現するために、みらい翻訳側の開発に頼るだけではなく、ユーザ企業も効果的なAI学習に必要な翻訳データ提供や利便性向上に向けたフィードバックを行うなど、開発側とユーザがタッグを組んで『Mirai Translator®』を進化させていくことが必要ではないかと考えています。